

横須賀中央駅から北へ中心街を10分ほど歩いたところに
米軍基地の正門があります。
この門から向こうは“日本ではなくて米国”となるわけですね。
何となく緊張感を感じます。
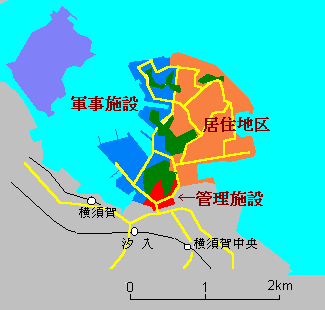
在日米軍横須賀基地は,横須賀市街中心部の北に突き出た半島
全部と,新井掘割水路によって田浦地区から切り離された島の部分とを
占める広大な敷地に広がっています。
その前身は言うまでもなく敗戦前の日本海軍の施設なのですが,
現在は基地内の居住区になっている半島東側には実は普通の町が
広がっていました。
つまり,米軍基地はそうした町も飲み込んで,
旧海軍以上の広い敷地を占めているわけです。

基地の東半分,半島側は大きく分けて3つの区域で構成されています。
正門を入ってすぐ,基地の南端部には 基地全体の管理中枢機能が集まっています。 その中心がこれ。 現在,在日米海軍の司令部として使用されているこの建物は 敗戦前は旧海軍の横須賀鎮守府の建物であったそうです。
戦後50年間にわたって米海軍がこの敷地を使いつづけているわけですが,
日本海軍時代の遺物も敷地内のあちらこちらに散在しているようです。

たとえば,これ。
本部の北東側,居住地区の入口近くにある将校用クラブの入口に
置いてある“方位盤”。
基地内の別の所から移設してきたものらしいのですが,
横須賀を基準に方位の書かれている地点が面白い。
布哇(ハワイ),大泊(南サハリン・コルサコフ)など。
「宮城」はどうやら「みやぎ県」ではなくて
「きゅうじょう」=皇居を指すようです。
(画像処理をしたら文字盤が見えにくくなってしまいました。)

ついでにもう1つ。 同じく将校用クラブの庭に何気なく置いてあるこの石には 「紀元二千六百年記念」という文字が刻まれています。
敗戦で何もかもが断絶したというよりも,
旧海軍時代からの連続性を物語るものがそこここに残されているのですね。
「軍港」という点で,横須賀は旧海軍時代も,
米海軍が主人となった戦後も連続している,ということでしょうか。

さて,司令部から西回りで敷地に入った半島の南西部が いくつものドックを備えた軍事施設になります。 ただ,戦艦や潜水艦が停泊しているほかは 特に普通の港と変わることはありません。
このあたりは旧海軍時代からの造船所やドックを
引き継いだところです。
多くの建物が戦後,米海軍によって建てられたと思われる中で,
空母インディペンデンスが停泊していたバース
(基地の中で一番大きい)の脇に建っていたこのクレーンは
旧海軍のものでした。
カメラの性能のせいで字がつぶれて読めなくなってしまったのですが,
中ほどに漢字で,しかも右から横須賀の海軍造船所のものである
ことが書かれています。
半島の北側から東側にかけての区域が居住地区になります。
横浜の山手や相模原にある米軍住宅と同じように
全体にゆったりとした配置なのですが,
横須賀の場合目立つのは,例の“思いやり予算”で建てられた
高層住宅。平地の乏しい横須賀では,やはり土地のやりくりに
苦労している,というところでしょうか。
それでも日本の公団住宅に比べたらずっと広そうだぞ。
半島の東側には子供たちのための学校があり, さらに売店地区にはアメリカらしくマクドナルドが しっかりと出店しています。 広々とした野球のグランドがあるあたりもアメリカらしいですね。 ある意味では当然なのかも知れませんが, 基地の中で一応生活に必要なものは一通り揃うようになっているようです。 ちょうど,クリスマスの前ということで, 基地のあちらこちらに各種のパーティーのお知らせを書いた 垂れ幕やポスターが出ていました。 (私はアメリカへ行ったことがないのですが) きっとアメリカの普通の町の年末風景と同じなのでしょうね。

ところでおわびなのですが, 初めにバスで基地の中を巡回した時に 手違いで写真を撮りそびれてしまいました。 そんなわけで,ここに掲載するべき写真があまりありません。 後で気づいて撮影したこの写真でお許しください。
これは前の説明で出てきた将校クラブ。
私たちはここで昼食を食べさせられました。
メニューは純アメリカ風ヒレ・ステーキ。
“将校用のお昼”ということのようですね。
ここでもクリスマス・パーティーが催されると書いてありました。
>> 空母インディペンデンス へ
>> はじめのページ へ戻る
1998. 1.28 野外研修委員会